公衆栄養学実習a(管理栄養士専攻3年)
食生活科学科助手R.K
今回は管理栄養士専攻必修授業の「公衆栄養学実習a」の授業風景をご紹介いたします。
この実習では、地域の健康・栄養上の課題に応じた公衆栄養プログラムの計画・実施・評価の総合的なマネジメントに必要な事項について理解を深めることを目的としています。
特に、集団の健康状態および食事・栄養素摂取状況に関する情報を収集・分析し、活用するための基本的技術を習得するための実習を行います。
また、管理栄養士として、主に行政の現場(保健所や保健センター等)において、健康の維持・増進のための栄養管理・指導に必要な知識・技能・態度を修得することを目指します。
この日の実習は「公衆栄養アセスメント(食事調査法)」について学び、24時間尿中食塩排泄量の測定、24時間思い出し法を行いました。
まず、実験室にて24時間尿中食塩排泄量の測定をします。
前日に、比例採尿器で24時間分の尿の1/50量を採取してきてもらいました。
実習では、イオンメータを用いてナトリウムとカリウムの濃度を測定し、前日1日の摂取量を推定します。

ナトリウムとカリウムの摂取量の推定が進むと、「思ったより塩分が少なかった!」「普段はこんな食事じゃないのに~!」など声が聞こえました。
次に、24時間思い出し法でペアとなった学生同士、実習前日の24時間に飲食したものを時間の経過に沿って聞き取り、食品の種類と重量を推定します。
食品重量の推定には、食器の大きさのスケールや料理カード、実物大の食品写真等を参考にします。

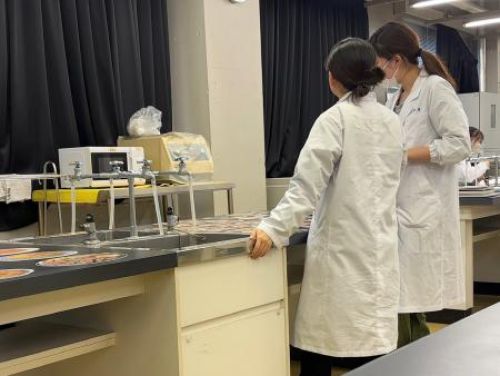
その後、聞き取った情報を基に栄養価計算を行います。
レシピが不明なもの、食品成分表に掲載されていない食品の扱いなど、計算の困難な事例は先生とも相談して対処していました。
最後に、2つの調査法で得られたナトリウムおよびカリウム摂取量が異なる原因を考察し、本日の実験は終了です。
24時間思い出し法でペアとなった学生同士はもちろん、クラスで協力し合っている姿が印象的でした。
来年度は4年生になり、国家試験対策も本格的に始まります。
今回学んだこと、今までの学校生活での経験を糧にして、これからもみんなで頑張っていってほしいと思います。







