人間社会学科「メディア社会論」で、テレビ朝日出前授業「テレビの災害報道2025 命を救う放送とは…」が行われました(6/6)
人間社会学部人間社会学科の駒谷真美教授が担当する授業「メディア社会論」で、テレビ朝日広報局の久慈省平氏を講師に迎えた出前授業が6月6日(金)、渋谷キャンパスで行われました。
前半は、久慈氏が災害報道の基本や災害発生時のテレビ局の対応を紹介し、能登半島地震と東日本大震災における報道対応を比較しながら、未曾有の災害発生時にテレビが果たすべき役割について解説。後半は、渋谷キャンパスで大地震が起きた場合を想定したワークショップを実施し、学生たちは災害を自分事として捉える視点や、日頃の備えの重要性を学びました。
この日の様子は、7月6日(日)のテレビ朝日の番組「はい!テレビ朝日です」で放送されました。
 「テレビ朝日 出前授業」の様子
「テレビ朝日 出前授業」の様子
授業「メディア社会論」とは
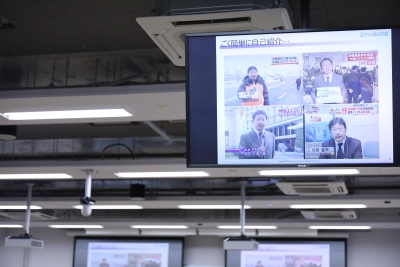 久慈氏の自己紹介
久慈氏の自己紹介
メディア社会がどのような構造によって成り立っているのかをテーマごとに掘り下げ、その実態を多角的に読み解いていく授業です。メディアが引き起こす社会現象を事例として取り上げ、過去の背景から現在の課題、さらには将来への影響まで検証しながら、情報社会に主体的に関わるための基盤となる「メディア情報リテラシー」を育むことを目的としています。
今年度の第8回目となるこの日の授業は、「疎外される社会」をテーマとした全5回シリーズの最終回。第1回から第4回にかけては、報道被害や情報格差、インフォデミック、フェイクニュースといったメディアの負の側面に焦点を当ててきましたが、この日は視点を転換し、メディアの持つポジティブな力に着目。人々の命を救う災害報道の可能性に迫りました。
ゲストスピーカーとしてお招きしたのは、災害報道担当部長として現場の最前線で指揮を執ってきた経験を持ち、防災士の資格も有するテレビ朝日広報局の久慈省平氏です。「テレビの災害報道2025 ——命を救う放送とは…」と題した講義をとおして、災害時におけるメディアの役割や、私たちが取るべき行動について解説いただきました。
進化する災害報道~「能登半島地震」と「東日本大震災」の報道を比較~
 進化する災害報道について話す久慈氏
進化する災害報道について話す久慈氏
通信社を経てテレビ朝日に入社し、「ニュースステーション」や「報道ステーション」のディレクター、BS朝日「ニュースアクセス」のコメンテーターなどを担当してきた久慈氏。東日本大震災では東北3県で現地デスクを務め、その後、災害報道担当部長や報道資料部長を歴任し、現在は広報局に在籍されています。
久慈氏はまず、これまで携わってきた仕事を映像で振り返った後、災害報道の基本である気象と地象の違いや、テレビ局が災害情報をどのように扱っているか、速報スーパーや地震・津波情報、台風の進路予想の報道の仕方について解説。緊急地震速報が出た際の対応や、アナウンサーが災害時に発するコメントのルールにも触れました。
その中で久慈氏が特に強調したのが、「災害報道はテレビの義務」であること。放送法や災害対策基本法に基づき、テレビ局には国民の生命と財産を守るための防災放送の提供が義務付けられていることを訴えました。
さらに久慈氏は、2024年に発生した能登半島地震と2011年の東日本大震災のテレビ朝日の対応を比較。東日本大震災での津波避難呼びかけ不足や、緊急性の低い情報の配信といった反省点を踏まえ、能登半島地震でどのように報道を改善したか、具体的な事例とともに紹介しました。大規模な災害発生に備え、日々緊急放送への対応訓練を行っていることにも言及し、学生たちに驚きを与えました。
もしも、渋谷キャンパスで巨大地震に遭遇したら!? クイズで学ぶ防災アクション
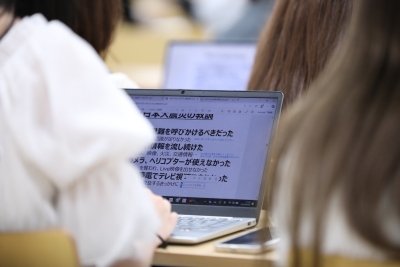 クイズで学ぶ防災アクション
クイズで学ぶ防災アクション
授業の後半は、学生たちが日常を過ごす渋谷キャンパスを舞台にした実践的なワークショップを実施。午前11時58分、東京23区が震源のマグニチュード7.3、最大震度7の大地震に遭遇したと仮定し、その時取るべき行動をクイズ形式で学びました。
「緊急地震速報が出たらバッグで頭を隠すか、すぐに教室から出るか」「揺れが収まったら階段で1階に降りるか、カフェテリアで待機するか」といった具体的な問いが投げかけられ、学生たちはRespon(出席カードやアンケートを提出・共有できる無料アプリ)を通じて回答。集計結果は即座に共有され、久慈氏が正しい行動とその理由をわかりやすく解説しました。身近な場所を想定したこのクイズは、学生たちが災害を「自分事」として捉える貴重な機会となりました。
質疑応答では、災害時に備えて「バッグに入れておくべきもの」の紹介も
 質問をする学生
質問をする学生
授業の締めくくりとして設けられた質疑応答では、学生から活発な質問が寄せられました。「外出中に大地震が起きた場合の避難場所は?」「災害時に備えてバッグに入れておくべきものは?」といった問いに対し、久慈氏は実践的なアドバイスを送りました。
たとえば、「バッグに入れておくべきもの」については、「携帯トイレ」「モバイルバッテリー」「現金(特に100円玉)」の3点を推奨し、「携帯トイレは常備しておくだけでなく、一度使い勝手を試しておくとよい」など具体的に説明。学生たちは、うなずきながら熱心にメモを取っていました。
なお、この日はテレビ朝日のカメラが入り、授業の様子を撮影。学生や駒谷教授のコメント映像も含め、7月6日(日)のテレビ朝日の番組「はい!テレビ朝日です」の中で取り上げられました。
出席した学生のコメント
 インタビューに応じる学生
インタビューに応じる学生
・東日本大震災と能登半島地震の報道の違いをあらためて比較してみると、能登半島地震では津波避難の呼び掛けの緊迫感がより増していることを再認識した。
・東日本大震災での反省点を踏まえ、テレビ局が災害発生時に即座に判断して行動できるよう、日々努力を重ねていることを知り感銘を受けた。
・日本では気象と地象を気象庁が一括して扱っているのに対し、海外では別の省庁が担当することもあると聞いて驚いた。
・災害に遭遇した際、自分が生き残れるように対策していきたいと思った。
・災害時に備えて携帯しておくと良いものが具体的に示され、大変参考になった。いつもキャッシュレス決済を利用していて、財布の中に現金が入っていないことがあるので気を付けたい
・次に大規模な災害が起きた際、正しい行動を取るためにどのような情報源から情報を得るべきか、深く考えるきっかけとなった。
テレビ朝日広報局 久慈省平氏のコメント
 テレビ朝日広報局 久慈省平氏
テレビ朝日広報局 久慈省平氏
大学卒業後、私は一貫してニュースの現場に携わってきました。現在は広報局に所属し、災害報道などをテーマにした“出前授業”の企画・実施を担当しています。
これまで、小学生から大学生、高齢者まで幅広い世代にお話しする機会がありましたが、特に思いを込めて伝えたい相手が、Z世代にあたる大学生の皆さんです。この世代の多くはテレビにあまり触れておらず、私自身も大学時代はテレビをほとんど見ていませんでした。だからこそ、テレビの面白さや社会的意義をきちんと伝えることが、今の自分の役割だと感じています。使命感を前面に出すつもりはありませんが、一人でも多くの若者にテレビへの興味を持ってもらい、「テレビにはこんな可能性があるんだ」と気付いてもらいたいという一心でこの活動を続けています。
今回の授業では、単にテレビ報道の仕組みを紹介するのではなく、「報道の現場で何が起きているのか」「どう判断し、どのように伝えているのか」といった核心部分に踏み込み、率直にお話しさせていただきました。情報感度の高い今の若者は、インターネットを通じて幅広い知識を得ており、テレビを無条件に肯定するような語りでは信頼を得られません。そのため、テレビが抱える課題や内部での葛藤についても包み隠さず正直にお伝えしたつもりです。
報道に関わる私たちもまた、日々悩み、失敗を重ねながら、より良い報道を模索し続けています。今回の授業をとおして、そんな“テレビのリアル”の一端が少しでも皆さんに届いたのなら幸いです。
人間社会学部人間社会学科 駒谷真美教授のコメント
 人間社会学科 駒谷真美教授
人間社会学科 駒谷真美教授
「メディア社会論」の授業では、シリーズの一つとして「疎外される社会」というテーマでメディアによる社会現象の事例を取り上げ、その背景や、現在生じている問題点、未来への影響や可能性を考察しています。これまで、「松本サリン事件を例とした報道被害」「東日本大震災に見る情報格差」「コロナ禍におけるインフォデミック」「現代社会にあふれるフェイクニュース」と、メディア社会のネガティブな側面を扱ってきましたが、一方でメディアには、時には人々の命を救うほどのポジティブな力があります。そこで、「疎外される社会」シリーズの締めくくりとしてテレビ朝日の久慈氏をお招きし、災害報道についてお話いただきました。やはり、報道のプロとして数々の災害に向き合ってきた久慈氏の言葉は学生たちの心にも強く響いたようで、授業が進むにつれ学生たちの目の色が変わっていくのが見て取れました。
後半のワークショップでは、渋谷キャンパスで大地震に遭遇したと仮定したクイズを通じて、災害時の具体的な行動を学びました。学生たちが普段過ごす場所でも災害が起こりうるという現実を再認識する貴重な機会となり、大変意義深い「命を守る」授業になったと感じています。







