電気通信大学との単位互換科目「環境デザイン特論a」の集中講義が行われました(8/6~8/9)
8月6日(水)から9日(土)までの4日間、環境デザイン学部環境デザイン学科の安齋利典教授が担当する「環境デザイン特論a」の集中講義が行われました。これは本学と電気通信大学との連携・協力協定に基づき実施された初の単位互換科目で、電気通信大学の2~4年生12名と本学の環境デザイン学科1年生13名の計25名が参加。ワークショップを中心に、デザイン思考を実践形式で体験しました。
座学とワークショップでデザイン思考を体感する4日間。1日目はオンライン、2日目は電気通信大学で開講
 電気通信大学での集中講義の様子
電気通信大学での集中講義の様子
デザイナーがモノやコトをデザインする際に、どのように相手の立場に立つか、相手の気持ちになれるか——。今年2月に本学と連携・協力協定を締結した電気通信大学との初の単位互換科目である「環境デザイン特論a」は、4日間の集中講義。初日の8月6日(水)はオンラインによる座学で、デザインとは何かという基本に始まり、デザインプロセスやHCD(人間中心設計)、UX(ユーザー体験)設計、サービスデザイン、企業経営へと拡張するデザイン思考を座学で学びました。
2日目の8月7日(木)は、電気通信大学で実施。「大学生活を充実させるためには」をテーマに、6つのチームに分かれてのワークショップがスタートしました。まずは、チームごとに課題を設定し、ブレインストーミングで意見を出し合うところから。続いて、付箋やカードに書き出したアイデアを関連性に応じてグループ分けしながら整理し、思考を体系的にまとめていくKJ法で問題点を把握。さらに、ほかのメンバーのアイデアを発展させるブレインライティングで課題解決の方向性を探りました。
この日の後半は、コンセプト立案に着手。ペルソナ法、シナリオ法、要件仕様を想定して、具体的なユーザー像やニーズを明確化。最終的に、コンセプトシートにまとめ上げました。
3日目、4日目は本学で課題解決に向けたサービスをデザイン
3日目、4日目の講義は本学で開講。3日目となる8月8日(金)は、顧客体験を可視化するカスタマージャーニーマップと提供するモノ・コトの設計図となるサービスブループリントを作成し、アイデアを落書きグラフィックで具現化。最後にカタログ型プロトタイプとして仕上げました。



そして、最終日となる8月9日(土)は、プロトタイプの評価を実施。課題点や改善案を整理し、コンセプトシート、カスタマージャーニーマップ、サービスブループリントなどを含めたポートフォリオを作成し、チームでプレゼンテーションを行いました。
各チームのプレゼンテーションのテーマは次のとおりです。
・「とぅもろーぷらんなー」~最高の1日を~
大学生活を計画的に楽しむためのアプリを提案
・授業を効率化するオンライン授業
Zoomを活用したオンライン授業提供システムを提案
・学生サークル紹介サイト
新入生向けサークル検索サービスを提案
・NISAについての基礎を知るアプリ
松尾芭蕉をキャラクターにした金融教育アプリを提案
・トラブル防止アプリ「fri END check」
人間関係トラブルの予防・解決支援アプリを提案
・課題解決フォーラム
人間関係トラブルの予防・解決支援アプリを提案



それぞれのチームが、日々の生活習慣、大学の学修環境、交友関係、金銭面、トラブル防止、学業支援など異なる切り口で大学生活を充実させるためのサービスを提案。発表後の質疑応答では、サービスの運営主体や収益モデル、セキュリティ対策など多岐にわたる質問が飛び交い、学生たちの主体的な姿勢がうかがえました。
学生たちによる相互評価の結果、1位は「NISAの基礎を学べるアプリ」、2位は「学生サークル紹介サイト」、3位は「トラブル防止アプリ」となりました。
最後に、安齋教授は「ブレインストーミングに始まる多様な手法を、卒業研究はもちろんさまざまな場面で応用してほしい」と結びました。
電気通信大学情報理工学域Ⅲ類2年 中川敬仁さんのコメント
 電気通信大学情報理工学域Ⅲ類2年 中川敬仁さん
電気通信大学情報理工学域Ⅲ類2年 中川敬仁さん
理工系の学部ではデザインを体系的に学ぶ機会が少ないため、今回の講義を知りぜひ参加したいと思いました。実際に4日間のデザインワークショップを体験してみて、多くの知見を得ることができたと感じています。
すぐに数式で答えを導く理工系の発想とは異なるデザイン思考のプロセスは非常に興味深く、新鮮なアプローチで課題に向き合う実践女子大学の学生の皆さんからも刺激を受けました。
今後、卒業研究で製品や技術の開発に取り組む際にも、ユーザー視点を重視したデザイン思考を積極的に取り入れたいと考えています。
環境デザイン学部環境デザイン学科1年 木島葉子さんのコメント
 環境デザイン学科1年 木島葉子さん
環境デザイン学科1年 木島葉子さん
安齋先生の「プロダクトデザイン概論」の授業が面白かったこと、電気通信大学の学生の皆さんと共に学べる機会に魅力を感じ、この講義を受講しました。4日間の集中講義は内容が濃く、アイデア出しの方法からやまとめ方、デザイン思考のプロセスまで、さまざまな知識を幅広く吸収することができました。
特に、異なる分野を学ぶ電気通信大学の皆さんとチームを組んだワークショップでは、新たな視点に触れると同時に、資料作りや共同作業の進め方についても多くの気づきを得られました。
今後、建築設計を学ぶ中でも「使いやすさ」を追求するデザイン思考を大切にしていきたいと思っています。
環境デザイン学部環境デザイン学科 安齋利典教授のコメント
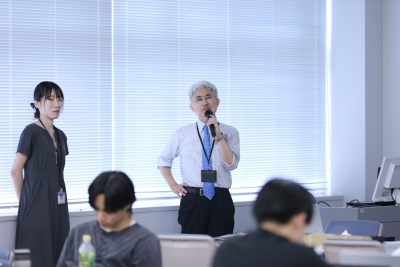 環境デザイン学科 安齋利典教授
環境デザイン学科 安齋利典教授
電気通信大学との単位交換協定の一環として、新たにデザイン思考に関する授業を企画・実施しました。初めての試みではありましたが、他大学や社会人を対象とした「デザインマネジメント」の講義を土台にシラバスを構築。デザイン思考の成功事例を単に紹介するのではなく、学生が主体となり考えるワークショップ形式を採用しました。
具体的には、デザイナーの役割やHCD、デザイン思考の概念といった基本的な部分から説明を始め、ハーバード大学やスタンフォード大学、ニールセン・ノーマン・グループの研究成果を引用して理論的な裏付けを示しました。また、ブレインストーミングをはじめ、問題発見と解決のフェーズから成る「ダブルダイヤモンドモデル」などの手法も身につけられるよう、実践を重視してカリキュラムを組みました。
授業の最大の目的は、デザイン思考の基本的なプロセスを体系的に理解してもらうことでしたが、本学と電気通信大学の学生の交流も大きな成果をもたらしたと感じています。異なるバックグラウンドを持つ学生同士が議論を交わすことで、一人では気づけなかった新たな視点が生まれ、互いの発想の違いが良い刺激をもたらしました。
この集中講義で学んだ思考法やアプローチを、今後の課題解決や卒業研究などでぜひ活用してほしいと思います。







