鈴木 浩明先生
研究テーマは、糖尿病の合併症を予測・予防すること。
糖尿病患者の転倒リスク研究は、世界から注目されました。
鈴木 浩明
Hiroaki SUZUKI
生活科学部 食生活科学科 教授
専門分野・専攻/臨床栄養学
Hiroaki SUZUKI
生活科学部 食生活科学科 教授
専門分野・専攻/臨床栄養学

[プロフィール]筑波大学医学専門群卒業後、筑波大学附属病院内科レジデントを経て、筑波大学大学院博士課程医学研究科生化系専攻を修了。筑波大学附属病院内分泌代謝内科医員、国立病院機構災害医療センター内科、筑波大学臨床医学系内分泌代謝内科助手、筑波大学臨床医学系内分泌代謝内科講師、筑波大学人間総合科学研究科内分泌代謝内科准教授、筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科准教授(組織改編)、筑波大学附属病院病態栄養部長を歴任後、2024年4月より現職。
「3つのポイントで分かる!」この記事の内容
- 専門は糖尿病。長年、基礎研究や臨床研究を続ける。
- 近年のテーマは、糖尿病合併症の予防と予測。
- 丸暗記ではなく「考える」臨床栄養学の授業を目指す。
最新の研究と出会い、臨床から研究の道へ

自然科学に興味を持つようになったのは、小学3年生の時。父に連れられて天体観測会に参加したことがきっかけで、天体や宇宙の仕組みに強い関心を抱くようになり、中学生の頃には将来は宇宙物理学者になりたいと思っていました。そんな私が医学の道に進もうと思ったきっかけは高校2年生の時、柳田邦男の『ガン回廊の朝』や西川喜作の『輝やけ我が命の日々よ』というノンフィクションに出会ったことです。だから最初は当然のように、臨床医になり患者さんの命を救うことを目指していました。
大学卒業後は研修医として筑波大学附属病院内科に勤務しました。今ではごく普通に使われているスタチンと呼ばれるコレステロール低下薬が発売された直後で、脂質代謝や動脈硬化の発症、進展に対する研究が急速に進み、予防医学という考え方が出てきた時期でもありました。そのタイミングで、松島照彦先生が米国留学から帰国し、筑波大学に赴任なさいました。先生の研究テーマは、分子生物学的手法を用いて脂質代謝異常の原因を探ること。冠動脈疾患に興味を持ち循環器内科医を目指してましたが、当時は新しい分野だった先生の研究に興味を持ち、内分泌代謝内科の大学院に入学することに。それが研究の道に進むきっかけでした。
動脈硬化の危険因子=Lp(a)を探る

大学院ではLp(a)という動脈硬化の危険因子となるリポたんぱく質の基礎および臨床研究をしていました。Lp(a)を形成するapo (a)は肝臓で作られのですが、apo (a)はヒトと旧世界サルにしか存在せず、apo (a)を十分に産生する培養肝細胞株が存在しないため、簡単に細胞実験や動物実験ができず、Lp(a)の代謝には不明な点が非常に多かったのです。感染症研究所でワクチンの検定のために解剖したカニクイザルの肝臓から初代培養肝細胞を培養するところから実験を始めました。肝臓の門脈という血管からコラゲナーゼというたんぱく質分解酵素を注入して肝臓の細胞をバラバラにするのですが、心停止して時間のたった肝臓ではコラゲナーゼ溶液が肝臓の隅々まで十分に行き渡らず、細胞の収量は十分ではありませんでした。試行錯誤の末にやっと十分な収量を得ることができ、インスリンがapo (a)の発現を転写レベルで増加させることを示しました。残念ながら、この研究は海外の大学に先を越されてしまいました。臨床研究は、糖尿病患者における血中Lp(a)濃度と糖尿病合併症との関連や、炎症で増加するIL-6が血中Lp(a)濃度与える影響なども研究しました。
大学院を修了後は、内分泌代謝内科の専門研修に入り、一時的に研究からは離れましたが、筑波大学に戻ってからは、分子生物学的手法を用いて2型糖尿病のインスリン抵抗性に関する研究を行ってきました。研究は、これまで明らかにされていないことについて仮説を立て、それを実際に確かめていく取組みです。このため、うまくいかないことや成果が出るまでに時間がかかることも多いですが、研究を通して知らないことを知る、分からないことが分かる、それが純粋に楽しい。だから教育や大学内での役割が増えて忙しくなってもできる範囲で研究を続けてきましたし、これからも続けていきたいと思います。
注目を集めた糖尿病患者の転倒リスクの研究
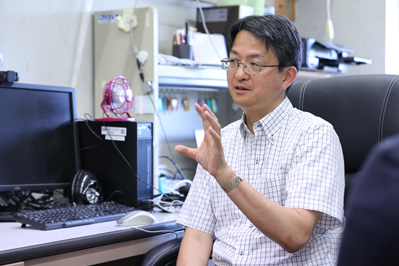
私が専門とする糖尿病は、インスリンの作用不足により慢性的に血糖値が高くなる病気です。高血糖状態が続くと血管が傷つき、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などの血管障害のリスクが高まります。そのリスクを「予測」することを近年の研究テーマにしています。具体的には頸動脈の動脈硬化の程度を評価することで、心臓を養う血管である冠動脈の動脈硬化の程度を予測する研究を行っています。
もう一つの研究テーマは「予防」です。筋肉にインスリンが作用しなくなると筋力が衰えて、転倒リスクが高まります。転倒を予防したいと思い、どのような糖尿病患者さんが転倒しやすいのか調べたところ、SGLT2阻害薬とGLP-1受容体作動薬という薬剤を使用している患者さんで、転倒リスクが有意に高まることが明らかになりました。これらの薬剤は血糖低下作用だけでなく、体重減少作用や心疾患予防作用、腎機能低下抑制などの作用があり、世界的にもたくさん使用されています。このため、世界的にかなり反響があり、論文が閲覧された回数は、同時期に発表されたすべての論文のなかでトップ3%にランクされました(340,520本中8,812位) 。また、転倒予防のための筋力トレーニングを遠隔で確認・管理するシステムの研究も行っています。
「自ら考える」授業を模索

筑波大学附属病院の理学療法士が普段の診療の中で糖尿病患者はバランス能力が悪く転倒しやすいと気づいたことが、転倒予防の研究を始めるきっかけになりました。研究を主導し、英語で論文を書いたのも彼です。このように、ちょっとした気づきや疑問が、研究や発見に結びつくこともあります。学生たちにも自分なりの視点やアイデアを大事にして考える習慣を身につけ、色々なことにチャレンジしてほしいと思っています。私が担当する臨床栄養学は覚えなければいけないことがたくさんあるので、ややもすると「丸暗記」が目的になりがちです。しかし、その覚えなくてはならないことの裏にはどんな理由があるのか考える習慣を身につけてほしいと考えています。講義でも、なるべく背景の情報から説明したり、最新の研究の内容を紹介したりするなど、日々の授業を工夫しています。また、新しい知見は英語で発表されることが多いです。今は翻訳ツールも栄養学や医学論文を十分な精度で日本語に変換してくれるので、英語に苦手意識があっても最新の知識に触れることが可能になっています。現在、ゼミ生と低糖質パンの研究をしていますが、自分で論文を探して翻訳ツールを使って論文を読み、パンの配合を考えてくれるようになりました。このように、自分で調べ、考え、試すことを通して、本当の学びや成長につながっていくのではないかと考えています。







