生活環境学科(現・環境デザイン学部環境デザイン学科)の目玉授業「生活環境プロジェクトb」の最終発表会が行われました(7/22)
生活科学部生活環境学科(現・環境デザイン学部環境デザイン学科)の2年生を対象とする、地域連携/社会連携のプロジェクト授業「生活環境プロジェクトb」の最終発表会が、7月22日(火)に行われました。今年度のテーマは、「世界で一番面白い『商店会』をつくろう!」。日野駅商店会の会員が所属する「ひのプロ」(日野宿通り周辺「賑わいのあるまちづくり」プロジェクト)の協力を得て、フィールドワークやグループワークを行ってきた学生たちが、ユニークな商店会の活性化アイデアを発表しました。
 日野市役所ロビーで行われた公開プレゼンテーション
日野市役所ロビーで行われた公開プレゼンテーション
「生活環境プロジェクトa、b」とは
2024年4月、「建築・住環境デザイン」「プロダクト・インテリア」「アパレル・ファッション」「総合デザイン」の4つのデザイン領域を学び、分野横断的な幅広いデザインスキルと多角的な視点を育むことを目指してカリキュラムを刷新した生活科学部生活環境学科(現・環境デザイン学部環境デザイン学科)。その特徴的な授業の一つが「生活環境プロジェクトa、b」です。これは専門分野の異なる複数の教員(安齋利典教授、一色ヒロタカ准教授、大川知子教授、塩原みゆき教授)が担当する領域横断型の授業で、デザインの力でリアルな社会課題を解決することを目標に、少人数のチームで地域連携/社会連携プロジェクトに挑みます。地域に根ざした大学の教育活動と地域の活性化への貢献が融合した、非常に意欲的な取り組みです。
 日野駅前東口広場で行ったオープン授業の様子
日野駅前東口広場で行ったオープン授業の様子
 生活環境プロジェクトaで行ったフィールドリサーチ
生活環境プロジェクトaで行ったフィールドリサーチ
新カリキュラム導入後、初の実施となった「生活環境プロジェクトa、b」の今年度のテーマは、「世界で一番面白い『商店会』をつくろう!」で、2年前に設立された日野駅商店会の活性化を目的としたプロジェクトです。かつて機能不全に陥っていた日野市内の4つの商店会を解体して誕生したこの商店会が、学生の若い視点やアイデアを求めていたことからスタートしました。
「生活環境プロジェクトb」に先立って開講された「生活環境プロジェクトa」では「ひのプロ」の協力の下、学生たちはフィールドリサーチやワークショップ、ヒアリングを通じてさまざまな情報を収集。商店会の課題を抽出し、現場視点での理解に努めました。続く「生活環境プロジェクトb」では、多様なデザイン手法を駆使して課題解決に向けたアイデアの提案に挑戦。この日の発表会では、8つのグループが考えたアイデアを、「ひのプロ」メンバー3名(野村智子氏、清水直氏、高畑勝氏)に説明しました。
発表会は2部構成。第1部は日野市の3拠点をZoomでつないだ斬新なプレゼン!

発表会は2部構成で、第1部は学生によるプレゼン。「街中での“ハプニングプレゼン”」をコンセプトに、日野市役所ロビー、日野駅前のリバーサイド(バー)、オステリア・リノ(イタリアンレストラン)の3拠点と日野キャンパスをZoomでつなぎ、合計4会場で実施しました。参加した学生は約60名。8チームに分かれ、3つの拠点から商店会活性化のアイデアを発表しました。
【チーム名:うなっこ/テーマ:ブランディング】
「商店街にはどのようなブランディングが必要か」
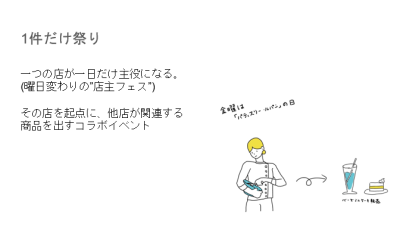
業種・業態が異なる会員で構成される商店会を「個性の集合体」と捉え、多様性を強みにしたブランディングで発展を目指すアイデアを提案。
【チーム名:るるここ/テーマ:SNS】
「商店会は知られているか?」
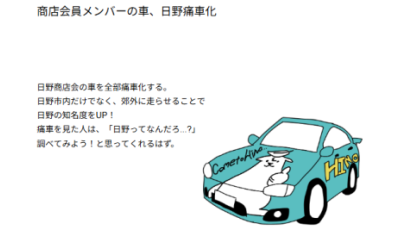
日野市民にはより深く日野を知ってもらい、市外の人には日野に訪れるきっかけとなるような、ユニークなメディア発信のアイデアを提案。
【チーム名:つながり/テーマ:つながり】
「商店会のつながりをつくる」
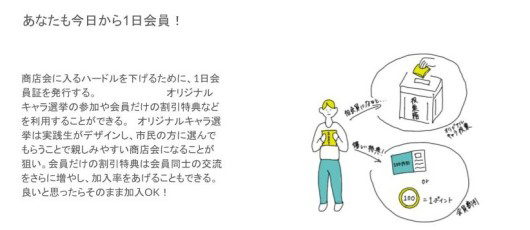
「人」「システム」「地図」「イベント」「コミュニケーション」「顔」の6つの入口を通して、商店会と人、地域を緩やかにつなぐアイデアを提案。
【チーム名:さくらもち/テーマ:水路】
「水資源が育む水路の庭」
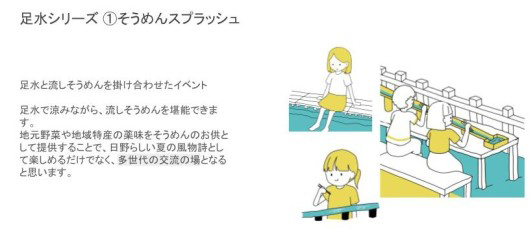
「水の郷百選」にも選ばれた日野の水源の魅力をPRし、水路を人と地域をつなぐ“庭”へと発展させ、地域の人々が自然と集まる場にするアイデアを提案。
【チーム名:チーム安心/テーマ:プロダクト】
「世界一面白い商店会のグッズ」
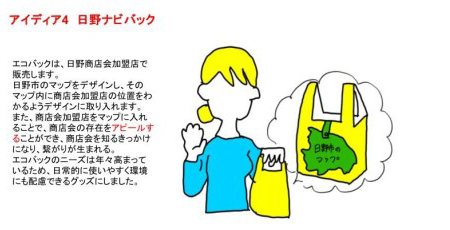
オリジナルキャラクター「のすけ」を考案し、「使える」「配りやすい」「楽しい」をコンセプトにしたグッズで商店会を盛り上げるアイデアを提案。
【チーム名:サラダパスタ/テーマ:空き店舗】
「シャッターをあけよう!」
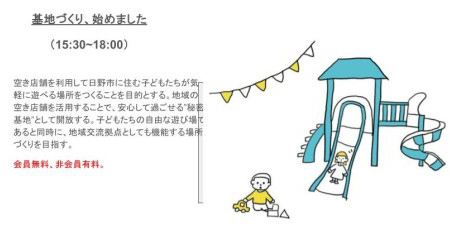
空き店舗を街に点在する“可能性のかたまり”と捉え、多様な活用法と「挑戦してみたい」という気持ちを後押しするアイデアを提案。
【チーム名:やきにく/テーマ:イベント】
「イベントで友達100人」
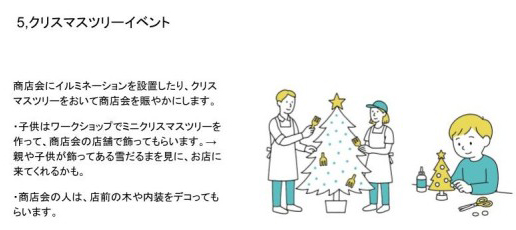
「ひのプロ」が主体となり、多くの人と“新しい何か”を共有できるイベントを開催。日野に多様なイベントの風景を作るためのアイデアを提案。
【チーム名:ごはん/テーマ:東口広場】
「駅前広場をメインフィールドに」

公共スペースである日野駅東口広場を活用して点在する商店会の店舗をつなぎ、にぎわいの発信源とするアイデアを提案。

第1部のプレゼンは、商店会のメンバーが各会場やZoomから参加できるほか、通りがかりの市民や市役所職員も日野市役所ロビーで自由に聴講できるスタイルを採用しました。実際に日野市役所ロビーでは、立ち止まってプレゼンを聞いてくださる方々がたくさんいらっしゃいました。今回のプレゼンは、大学が地域と連携し、実践的教育に取り組んでいることを広く発信する絶好の機会となりました。
2部は対話型ワークショップ形式での講評

プレゼン後は日野キャンパス本館1階のキャンパススクエアに会場を移し、ワークショップ形式での講評会を実施。壁に掲示した各チームのプレゼン資料を見ながら参加者全員でアイデアを共有し、「ひのプロ」の3氏が学生たちにフィードバックを行いました。学生から個人的に推しているアイデアをアピールする場面もあり、対話を通して全員で実現の可能性を探りました。
総評では、各氏から次のような貴重なアドバイスが寄せられました。
「似たようなアイデアもあったが、それぞれ異なる視点でアプローチしているのが良かった。他チームとの相乗効果が期待できるアイデアも多く、組み合わせて実現できたらいい」(清水氏)
「授業が進むにつれて皆さんの考え方が洗練されていった。アイデアに込めた思いも伝わり、充実した授業になったと感じる。実現をサポートしていきたい」(高畑氏)
「『生活環境プロジェクトa』でのリサーチが今回のプレゼンに生かされていた。視点が多様化し、ポジティブなアイデアが多いのは良かったが、プレゼンスキルはまだ伸ばせる。今後も努力を続けてほしい」(野村氏)
学生の自由な発想とデザインの力で、日野駅商店会の未来を切り開く!

最後に一色准教授は、「すぐに実現できそうなアイデアがたくさんあったが、それをいかに実践していくかがポイント。大学、ひのプロ、日野駅商店会で協力して進めていきたい。授業は今回で終わるが、リアルに社会を動かす取り組みとして続けたい学生がいればぜひ手を挙げてほしい」と呼び掛けました。
なお、「生活環境プロジェクトa、b」は、次年度からは環境デザイン学部環境デザイン学科の目玉授業「環境デザインプロジェクトa、b」として開講予定です。この授業の中で、今回のアイデアを実行に移すことも検討されています。また、今回の取り組みを卒業研究のテーマに設定している学生もおり、大学と日野駅商店会のさらなる連携が期待されています。
さらに今回のアイデアは、授業の中で参考にした書籍『次の野球』(横浜DeNAベイスターズ著。進化するプロ野球の在り方を探るアイデア集)にならい、1冊のアイデアブックとしてまとめる計画です。
学生のコメント

私のチームは、「駅前広場をメインフィールドに」というテーマで発表しました。みんなで役割を分担する中で、私はプレゼン資料のイラストを担当させていただきました。完成させていく中で苦労したことは、ほかの班よりもアイデア数が多く、それを捨てることができなかったことです。多くアイデアを出したため、全体に統一感を出すことが大変でした。また、中間発表の講評で、「イベントの提案になっている」と指摘を受け、商店会の皆さんの意見を軸にアイデアを練り直しましたが、「駅前広場といえば日野駅商店会」と直結するようなアイデアをもっと出せたのではないかと反省しています。個人的には、大学でのアパレル関係の学びを生かし、駅前広場でファッションショーを開催してみたいです。(生活科学部 生活環境学科2年 小坂亮子さん)







