竹内 光悦先生
人の行動や意識をデータ化して、その特徴を捉えるデータサイエンス教育を考える

竹内 光悦(TAKEUCHI Akinobu)/社会デザイン学科
鹿児島大学理学部、理学研究科、理工学研究科を修了。博士(理学)を取得。数学の教員免許を取得しながら、専門社会調査士も取得し、調査や分析を用いたデータサイエンス教育を研究中。立教大学社会学部助手を経て、2004 年から実践女子大学人間社会学部専任講師・同准教授就任。他大学や公的機関・企業等でも、調査・分析系の授業や講演を担当。その他、統計関係の検定試験やグラフコンクールに関係し、ワークショップやデータコンペティションの事務局等にも従事。
Q1. 先生の研究分野は何ですか。その研究を始めたきっかけは何ですか
研究分野は統計科学です。統計科学では、様々な分野で問題解決を目指すために、データを適切に集めたり、分析することを研究します。ざっくばらんにいえば、調査と分析に関する研究をする分野といえばわかりやすいでしょうか?人間社会学部では、人間社会で起こり得る問題や課題について、より適切にデータに基づいて説明・解明していくことを目指しています。また研究のきっかけですが、もともとは数学を学んでいたのですが、コンビニの発注業務などを体験し、マーケティングや消費者心理に興味を持ち始め、統計科学を研究するようになりました。
Q2. 先生が担当されている授業の中で、学科を決める1年生やゼミを決める2年生におススメの授業は何ですか
人間社会での諸問題を解決するためには情報収集やデータ分析が科学的なアプローチとして必須です。そのことを踏まえ、1年前期の「社会調査概論」、1 年後期の必修科目の「社会と統計」を初めてとして、本学部では社会調査士関連の科目を体系的に配置しています。これらを1 年次から順に受講することをお勧めします。
Q3. 先生のゼミはどのような活動をしていますか。どんな雰囲気ですか
私の「行動計量学ゼミ」では、計量的なアプローチで人間社会を研究します。世界的に多くの企業で DX をはじめ、多くの企業で業務のデジタル化が進み、AI などを活用することで、働き方や働く場が大きく変わってきています。そのような社会の中で、人の行動や意識を適切に測り、そのデータに基づき問題発見、企画提案ができる人材を社会は今後ますます期待し、特に実践的な経験を望まれます。そこでゼミではこのことを踏まえ、関連知識やスキルは授業で紹介しつつ、ゼミでは体験・経験を積むために、企業連携を踏まえた PBL や学外のコンテスト・コンペティションに積極的に参加しています。ゼミの雰囲気ですが、グループワークが多いため、ゼミ生同士も楽しくしています。ゼミ生からは「普段はのんびりしているが、やるときはやるゼミ」といわれています。卒業生の話でも大学でどのような活動をしたかをとても実感できるゼミとして満足度が高い(ガクチカで困ったことはないとも)といわれています。



Q4. 先生のゼミでは、どのような卒業論文のテーマがありますか
行動計量学のため、計量的なアプローチが必須ですが、分野としては消費者購買行動をはじめとするマーケティング関係(マーケティング・リサーチやマーケティングデータ分析、など)、対人心理の測定や尺度構成など心理関係、地域や女子社会に起こっている社会問題に対する意識を測ったり、分析して地域創生を目指す社会関係など、多種多様なテーマがあります。最近の竹内の研究である統計・情報教育に関係するデータサイエンス教育のテーマもあります。他の大学の行動計量学ゼミでは、テキストマイニングなどを使った歌詞の傾向分析やアイドルの特定の行動(しぐさ)と売り上げの関連分析、など、生活に身近なテーマの卒論も多数あります。
Q5. 先生の大学時代の楽しかった思い出は何ですか
学部時代はアルバイトでの人間関係の構築が楽しかったですね。大学院生時代、私は地方大学にいたこともあり、その場にいても交流ができないため、海外を含め、国内外の多くの学会で研究発表をしていました。飛行機の中で発表スライドを作るなどことも結構あり、常に走り続けたという感じがします。今のショートスリーパーの体質を作ったのもこの時期かもしれません。その結果、それぞれが楽しい思い出と感じています。
Q6. 受験生に人間社会学部に入学したら、どのような学生になってほしいですか
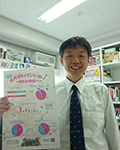
私自身、高校までも頑張っていたと思うのですが、大学で社会に触れる機会も触れ、人との交流を強く意識し、社会での活躍を見据えた学びや体験をし、価値あるものと感じています。そのためみなさんにもそれらの体験をし、その中で自分に足りないことがあれば、それらを学び、自分のいいところがあればさらに伸ばすなど、時間を無駄にせず、自分のレベルアップを日々感じてほしいと思います。







