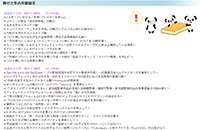駒谷 真美先生
メディア社会の!(ビックリ)と?(ハテナ)を一緒に考えていきましょう!

駒谷 真美(KOMAYA Mami)/人間社会学科
お茶の水女子大学大学院 博士(学術)取得
Mills College Graduate School, USA, Master of Arts(Early Childhood Education)取得
聖心女子大学大学院 文学研究科 国文学専攻 修士課程修了/ 文学修士取得
[参考資料]
Link Click!☞ 平成29年度 ベストティーチング賞
Link Click!☞ researchmap https://researchmap.jp/komayamedialab1
Link Click!☞ 駒谷メディアラボHP https://www.komayalab.com/
Q1. 先生の研究分野は何ですか。その研究を始めたきっかけは何ですか
メディア情報リテラシー(Media and Information Literacy)「メディアと楽しく上手につきあう」研究をしています。
米国で大学院生の頃、付属幼稚園でアシスタントティーチャーをしていて、園の子ども達が当時大人気の幼児番組「Barney & Friends」に熱狂するBarney phenomenonに遭遇しました。そこで、今どきの子どもとメディアの関わりについて、追究しようと思いました。
Q2. 先生が担当されている授業の中で、学科を決める1年生やゼミを決める2年生におススメの授業は何ですか
1年生の『人間社会学総論』では、両学科の教員が担当するので、学科の雰囲気がよくわかります。駒谷の担当回では、1年生のみなさんがメディアの落とし穴にはまらないように、SNSの危険について学習します。2年生の『メディア社会論』では、フェイクニュースなど社会問題を取り上げ、メディアの裏側を解明しています。『メディア心理学』では、赤ちゃんからお年寄りまで世代別にメディア観や情報行動について学びます。
 授業風景
授業風景
 『メディア心理学』の授業
『メディア心理学』の授業
Q3. 先生のゼミはどのような活動をしていますか。どんな雰囲気ですか
 駒谷ゼミ2023
駒谷ゼミ2023
 『渋谷のJJラジオ』番組表
『渋谷のJJラジオ』番組表
まず個人の活動としては、3・4年生の2年間でゼミ生は自分が大好きなコトをとことん研究し卒論にしていきます。次にグループ活動としては、大学公認ラジオ番組『渋谷のJJラジオ』(「JJラジオ1」担当)を企画取材制作し、月一で生放送しています。メディアの受け手・使い手・作り手・送り手の体験を通して、メディア情報リテラシーを身につけています。動画やブックを制作しインスタやラボHPなどで発信したり、常磐祭で発表したりしています。
Link Click!☞ 駒ゼミの活動
Link Click!☞ 駒ゼミのメディア活動
 駒ゼミ生研究活動
駒ゼミ生研究活動
 ラジオ取材(NHKイベント)
ラジオ取材(NHKイベント)
Link Click!☞ 駒ゼミ 年間活動レポート:ゼミのメディア活動と卒論研究を記録
 2023年度
2023年度
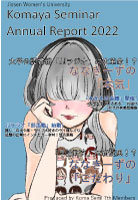 2022年度
2022年度
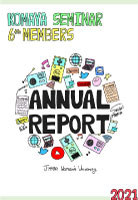 2021年度
2021年度
 2020年度
2020年度
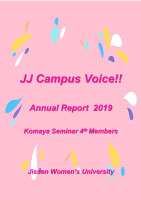 2019年度
2019年度
Q4. 先生のゼミでは、どのような卒業論文のテーマがありますか
駒谷ゼミはメディアゼミなので、卒論のテーマは、「ゼミ生の研究関心 ✕ メディア」であれば、基本的に自由です。「これはメディアとどう結びつく?」「このブームにメディアの影響がある?」など、ゼミ生なりの独自の視点で、WEBアンケート・メディア関係者インタビュー・文献研究に取り組んでいます。詳しくは、駒谷メディアラボHPの「駒谷ゼミについて」ページに、代々の駒ゼミ生の卒論リストを掲載しています。
Q5. 先生の大学時代の楽しかった思い出は何ですか
漫画研究会を皮切りに歌舞伎研究会や能楽研究会にも所属し、耽美派オタク道を邁進していました。クロード・ルルーシュ監督の仏映画『愛と悲しみのボレロ』に陶酔し、パリのシャイヨー宮まで聖地巡礼に行きました。20世紀バレエ団の美形ソリストのジョルジュ・ドンが深紅の円形舞台でボレロを踊った圧巻のラストシーンを思い出しながら、その舞台が設置されていた大理石の床を撮ってくるような、アクティブ?オタでした。
Q6. 受験生に人間社会学部に入学したら、どのような学生になってほしいですか
人間社会学部の講義や行事は、基本的にグループワークやPBL(プロジェクト学習)が多いので、色々な人たちと関わることができ、一緒に課題を成し遂げた達成感は、まさにプライスレスです。もちろん意思疎通が上手くいかない場合も多々あります。その試行錯誤を重ねてレジリエンス(打たれ強い心)を養い、ハプニングやアクシデントも乗り越えて「ピンチはチャンス!」と前向きにgutsでやりぬく学生になってほしいです。