田中 瑛先生
メディアを読み解き、メディアを使って社会を揺さぶる人へ!

田中 瑛(TANAKA Akira)/社会デザイン学科
2016年慶應義塾大学経済学部卒業(同メディア・コミュニケーション研究所研究生課程修了)、2022年東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(社会情報学)。九州大学大学院芸術工学研究院助教を経て、2024年より社会デザイン学科専任講師。
Q1.先生の研究分野は何ですか。その研究を始めたきっかけは何ですか
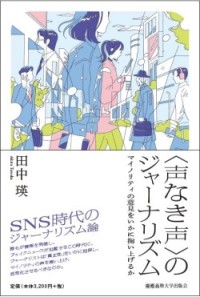
メディア・コミュニケーション、特にSNS時代のジャーナリズムを社会学的な視座から研究しています。大学生の時に報道記者を志して勉強する過程で、メディアが拾い上げられていない意見や「声なき声」をどのように拾い上げればよいのかに関心を持ったのがきっかけで、研究者の道を歩み始めました。自分たちの社会のあり方を自分たちでデザインする。そうした民主主義社会を持続させるには、多種多様な経験や背景や意見を持つあらゆる人々の対話が必要だという意識から研究を発展させてきました。
Q2.先生が担当されている授業の中で、学科を決める1年生やゼミを決める2年生におススメの授業は何ですか
おすすめの授業は前期の「メディア・コミュニケーション論」と後期の「メディア・ワークショップ」です。前期はメディアを自分なりの仕方で読み解くための知識を身に付け、後期は実際に具体的なアイディアを出し合いながら相互理解や対話の場をデザインしてみます。自分自身が日々触れているメディアについて「おや?」と思う気づきを共有しながら、楽しく学びましょう。
Q3.先生のゼミはどのような活動をしていますか。どんな雰囲気ですか
ゼミは2026年度から始まる予定です。大まかには3年生はグループ研究、4年生は卒業論文に向けて活動を進めるつもりです。それぞれが関心を寄せる「メディアに関するモヤモヤ」(日常的なコミュニケーションから政治や社会問題まで何でも)を持ち寄って、じっくり本を読んだり、記事や映像コンテンツ、SNSの投稿などを分析しながら、理解を深めていきます。皆さんの希望に応じて、一緒に実際に現場を見に行ったり、話を聞いたり、コンテンツを作ってみる経験も重ねていきましょう。気楽な雰囲気で互いに教え合う、話し合うことができれば嬉しいです。
Q4.先生のゼミでは、どのような卒業論文のテーマがありますか
新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などの伝統的なものからSNSやAIなどの先端的なものまで、「メディアに関わること」を幅広く歓迎します。例えば、特定の個人・集団や出来事がメディアの中でどのように描かれてきたのか、メディアを用いてある社会課題を発見したり解決するには何が必要なのか。卒業論文のテーマを選ぶうえで重要なのは、自分自身が心の底からのめり込める、自分ならではの問題意識を探し出すことだと思うので、より真剣に取り組めるテーマを一緒に探し出していきましょう。
Q5.先生の大学時代の楽しかった思い出は何ですか
大学生の頃には雑誌をつくるサークルに所属し、締め切り前になると慌ただしく編集するような日々を送ったのを思い出します。時には仲間と息抜きに旅行に行ったり、一人でいる時には喫茶店でまったりと本を読んで過ごしたりもしました。学部時代・大学院時代のゼミでも色々な意見に触れ、議論をする仲間ができました。この時に得られた自由気ままな読書時間は研究の土台になり、長い付き合いになる大学・大学院時代の親友たちは励みになる存在です。
Q6.受験生に人間社会学部に入学したら、どのような学生になってほしいですか
自由で楽しい大学生活の中で、今の自分とは異なる立場や経験を持つさまざまな人の立場の声を見聞きしながら、視野を広げてみてください。確実で当たり障りのないこと、「タイパ」「コスパ」が必要以上に追い求められる世の中ですが、他者への共感を押し広げるためにも、「わからないこと」「不確実なこと」を一つでも見つけて熱中してほしいなと思います。







